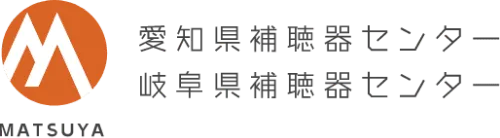公開日:
2017年7月にロンドンで開催された国際アルツハイマー病会議(AAIC)では「難聴を持つ人は、一般的な聞こえの人よりも軽度認知症を患う可能性が3倍高い」ことが発表されました。
(参考:NEW REPORTS FROM THE ALZHEIMER’S ASSOCIATION INTERNATIONAL CONFERENCE® 2017 FOCUS ON LIFESTYLE, RISK REDUCTION, IMPROVED DIAGNOSIS AND EARLY DETECTION)
「なんとなく聞こえにくい」程度の難聴であっても、認知症リスクとなりえます。
このようなニュースを聞くと、ご自身のみならずご家族で聞こえに問題がある方の認知症が心配になるのではないでしょうか。
本記事では認知症と難聴の関係、難聴のセルフチェック方法、そして補聴器装用を嫌がるご家族様への対策を解説しています。
難聴が原因となる認知症進行を防止して、家族みんなが楽しく安心できる環境を作っていきましょう。
難聴が認知症リスクを高める理由

2015年に厚生労働省が発表した新オレンジプランの中で、初めて難聴が認知症の危険因子として加えられました。
また、海外医学雑誌THE LANCETによると「医学的介入ができる認知症の原因」では、難聴がトップの9%(※のちに2020年の調査にて8%に改定)となっており、難聴が認知症に大きく影響していることがわかります。
難聴が認知症の進行を高める理由には、以下の2つがあります。
・音による刺激が減り神経細胞が衰える
それぞれ詳しく解説します。
コミュニケーションがとりにくく孤立する
難聴の方は、コミュニケーションがとりにくく、孤立しやすい傾向にあります。
難聴が原因で外出先でのコミュニケーションが上手く取れず、
「皆で会話をしていても内容が解らないので黙ってしまう」
「何度も聞き返すので、皆に相手にされなくなってしまった」
という経験から外出をしなくなってしまいます。
更にご自宅で一緒に暮らすご家族にとって、何度も同じ発言を聞き返されたり、大音量のテレビを一緒に見るのは大きな負担となります。
「聞き返されるのが面倒だから話しかけないでおこう」
「一緒の部屋でテレビを見るのはやめよう」
という事になりコミュニケーションが減るので、気付いたら難聴の方が孤立してしまうケースも少なくありません。
人は耳から入った言葉を脳内で理解し、また言葉に変換してコミュニケーションを図っています。
したがって、話しかけられる回数が減ると思考の回数が減り脳の機能も衰えます。
そればかりか、孤立が原因で抑うつが起こり、抑うつから認知症の原因となることもあります。
このように、難聴による孤立や、コミュニケーション不足は認知症の発生と進行に大きく関わっています。
音による刺激が減り神経細胞が衰える
音による刺激が減り、神経細胞が衰えることも認知症に関係していると言われています。
わたしたちの耳は絶えず音を感知し、脳で情報を処理しています。
ところが、難聴によって音による脳への刺激が減ると、脳の情報処理回数が減るため、神経細胞の働きが衰えます。
運動をやめて筋肉が衰えると、外に出るのがおっくうになるように、神経細胞の衰えがさらに認知機能の低下を加速させる可能性も高いです。
だからこそ聞こえにくいと感じたら、早急に対応しなければいけません。
加齢性難聴のセルフチェック

加齢性難聴とは、加齢によって蝸牛(内耳にあるかたつむり状の器官)の中の有毛細胞がダメージを受け、音の感知・増幅に問題が起こり生じる難聴です。
加齢性難聴の特徴は「高音が聞こえにくい」ことです。
ここからは、加齢性難聴のセルフチェック項目を紹介します。
□後ろからの呼びかけに気づきにくい
□聞き間違いが多い
□車の接近にまったく気が付かなかった経験がある
□話し声が大きいと指摘されたことがある
□集会や会議など、複数人の会話が上手く聞き取れない
□電子レンジの音やドアチャイムが聞こえにくい
□相手の発言を推測で解釈していることがよくある
□テレビ・ラジオの音が大きいとよく指摘される
(参考:一般社団法人 日本耳鼻咽喉科頭頚部外科学会 「聞こえ」をセルフチェック!)
ひとつでも当てはまった方は、聞こえに問題があるかもしれません。
認知症かも?難聴の方が補聴器を嫌がる原因と対策

難聴が認知症のリスクになると聞くと
「うちの親は大丈夫かしら」
と心配になる方もおみえになるでしょう。
特に、親御さんに認知症の兆候がすでにある場合、難聴によって認知症が進行する可能性があるため、注意が必要です。
難聴の改善に補聴器も有効な手段となります。
しかし、補聴器は依然としてご高齢者に受け入れられ難い傾向があります。
もし親御さんに補聴器を勧めても、拒否反応を示されてしまうかもしれません。
そこで、ここからは難聴の親御さんが、補聴器を嫌がる原因と対策を紹介します。
自覚がない:一緒に聞こえのチェックを受ける
補聴器を嫌がる原因のひとつに「自覚がない」が挙げられます。
周囲が気を遣って大きく、ゆっくり話していると、案外自分が難聴だということに気付きにくいからです。
その場合、前述した「加齢性難聴のセルフチェック」を一緒に受けてみましょう。
しかし、難聴の自覚のない方に「耳が遠くてコミュニケーションが困難」とストレートに伝えてしまうと、心を閉ざしてしまうかもしれません。
「もっと色々な話がしたい」というように、やんわりと伝えましょう。
お孫さんに「もっとおじいちゃん(おばあちゃん)と話がしたい」と言ってもらうのも有効です。
補聴器が恥ずかしい:おしゃれな補聴器をすすめる
「難聴」=「老人」のイメージを持たれている方もいます。
まずは、加齢性難聴は50歳ごろから始まることを伝えて、難聴だから老人ではないことをしっかり説明しましょう。
また、今は目立ちにくい補聴器や、ファッション性の高い補聴器など、補聴器自体の種類も豊富です。
補聴器が昔の「大きい」「邪魔になる」「かっこ悪い」といったマイナスイメージをお持ちの方もいますので「一度実物を見てみよう」と誘うのもおすすめです。
▶補聴器にはどんな種類がある?補聴器の特徴や価格・メリットを解説
費用が心配:補聴器をプレゼントする
ご高齢で年金暮らしの場合、補聴器の値段がネックとなって「まだ聞こえる」と強がっている可能性もあります。
お金の話はデリケートなので、子どもに相談しにくい、という方も多いでしょう。
このような場合は、思い切ってお子さんから補聴器をプレゼントするのも1つの手段です。
「高いから申し訳ない」
と最初は断られるかもしれませんが、
「これからもずっと相談に乗ってほしい」
「交通事故に遭わないようにお守りにしてほしい」
など、伝え方を工夫すると、親御さんも補聴器を受け取りやすくなるでしょう。
認知症と難聴|まとめ
認知症は、難聴によって深刻化しやすいことを紹介しました。
難聴は放っておくと改善が難しくなるので、早めの補聴器装用をおすすめします。
1990年にQOL(Quality of Life:生活の質)に問題を感じている、194名の退役軍人を対象に行われた、補聴器の装用と認知機能低下を調べるランダム実験では、補聴器を装用したグループで①社会的・情緒的機能②コミュニケーション③認知④抑うつの各項目に改善が見られました。
(参考:小川 郁『認知症と加齢性難聴―認知症予防対策における補聴器の役割―』
わたしたちが普段無意識に感じている、小鳥のささやきや風の音、他人の話し声でも脳は刺激を受け、活性化しています。
したがって、聴器で聴覚刺激を補うことが、認知症の予防に役立つと考えられるのです。
聞こえに問題のある方の中には、難聴に自覚がない場合と、補聴器に対して心理的・経済的ハードルを抱えている場合があります。
それらの対策にはご家族の方が積極的に補聴器をすすめていく事が、一番です。
食事やお茶に出かけるついでに、補聴器を一緒に見てみる、一緒に補聴器相談の予約を取るなど、工夫をしながらご家族へ補聴器の利用をすすめてみましょう。
補聴器センターには聞こえの専門スタッフが常駐していますので、まずは聞こえのお悩みをお聞かせください。
現在の生活環境など、お困りごとをより詳しく伺うために、来店予約をおすすめしています。
下のボタンからお客様のご都合のよい日時をお知らせください。
聞こえのプロがお待ちしております。