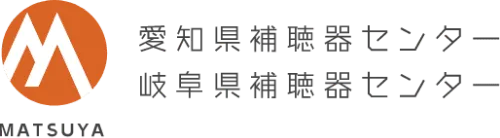公開日:
更新日:
「最近、家族との会話が聞き取りにくい」「テレビの音量が大きくなってきた」そんな悩みを抱えていませんか?
実は、難聴は40歳代から徐々に進行し始め、70歳代では約7割の方が経験する一般的な症状です。
この記事では、難聴の基礎知識から補聴器選びまで、誰にでもわかりやすく解説していきます。
難聴の症状と原因を理解しよう

加齢や騒音など、難聴には様々な原因があります。まずは自分の症状を理解することから始めましょう。
難聴の基本的な症状
日常生活で感じる代表的な症状には以下のようなものがあります。
- 人の声が聞こえにくい(特に子供や女性の声)
- 騒がしい場所での会話が困難
- テレビの音量が以前より大きくなっている
- 電話での会話がストレスに
このような症状が3ヶ月以上続く場合は、専門医への相談をおすすめします。早期発見・早期対応が、より良い聞こえの改善につながります。
難聴の主な種類と原因
難聴は大きく分けて「感音性難聴」と「伝音性難聴」の2種類があります。感音性難聴は内耳や聴覚神経の問題で起こり、加齢や騒音が主な原因です。一方、伝音性難聴は外耳や中耳の問題で、耳垢の詰まりや中耳炎などが原因となります。
年齢別の難聴の特徴
聴力の低下は30歳代から始まり、年齢とともに進行していきます。40歳代では高音域から聞こえにくくなり始め、60歳代になると会話音域にも影響が出てきます。70歳代では男性の約8割、女性の約7割が難聴を経験します。
難聴のための補聴器の基礎知識

補聴器は単なる音の増幅器ではありません。最新のデジタル補聴器は、装用者の聴力に合わせて音を調整する高度な機能を備えています。
補聴器の基本機能
現代の補聴器は5つの基本部品で構成されています。
- マイクロフォン(音の入り口)
- アンプ(増幅器)
- スピーカー(音の出口)
- 電池(充電池)
- コンピューターチップ
これらの部品が連携して、装用者に最適な音を届けます。騒音を抑制したり、会話音声を強調したりする機能も搭載されています。
タイプ別の特徴と選び方
補聴器は主に以下の3タイプがあります。
- 耳あなタイプ:目立ちにくく、メガネと併用しやすい
- 耳かけタイプ:操作が簡単で幅広い聴力に対応
- ポケットタイプ:操作が容易で高出力が可能
生活スタイルや聴力レベルに応じて、最適なタイプを選びましょう。例えば、着け心地良く使いたい方は耳かけタイプが、外見を気にされる方は耳あなタイプがおすすめです。
最新機能と価格帯
最新の補聴器にはスマートフォンとの連携機能やAI機能が搭載されています。価格は片耳5万円から50万円程度まで幅広く、機能や性能によって選択できます。高価格帯の製品ほど、騒音抑制や音声認識の精度が高くなります。
補聴器導入の流れと注意点

補聴器の選定には、専門家との綿密な相談が欠かせません。どういった場所やお相手が聞こえづらいか、細かく専門家へ伝えましょう。
導入のために
補聴器を選ぶ前に聴力測定を実施します。
- 気導閾値測定
- 骨導閾値測定
- 語音弁別能測定
これらの結果をもとに、補聴器の選定を進めていきます。検査結果は、その後の補聴器選びや調整の重要な指標となります。
選定時のポイント
補聴器を選ぶ際は、使用環境や目的を明確にすることが大切です。職場での使用が多い方、音楽を楽しみたい方など、ライフスタイルに合わせて機種を選びましょう。また、将来的な聴力の変化も考慮に入れる必要があります。
試聴とフィッティング
補聴器は必ず試聴するようにしましょう。専門スタッフによる細かな調整を行うことで、最適な音環境を作り出します。気になる点は専門スタッフへお伝え下さい。調整により可能な限り解決いたします。
補聴器の使用方法とケア

毎日快適に使用するために、正しい取り扱い方法を身につけることが重要です。初めは戸惑うことも多いかもしれませんが、徐々に慣れていきましょう。
日常的な使い方
補聴器の電源の入れ方や音量調整など、基本的な操作方法をマスターしましょう。慣れるまでは、静かな環境から使用を始めることをおすすめします。徐々に使用時間や場面を増やしていくことで、自然な聞こえに近づいていきます。
メンテナンス方法
長く使用するために、以下のような日々のお手入れが欠かせません。
- 就寝時の電源オフ
- 定期的な清掃
- 湿気対策
これらの基本的なケアで、補聴器の寿命を延ばすことができます。特に湿気は補聴器の大敵です。専用の乾燥ケースの使用をおすすめします。
長期使用のポイント
定期的なメンテナンスチェックを受けることで、常に最適な状態を保つことができます。また、使用環境の変化に応じて、適宜調整を行うことも大切です。3ヶ月に1回程度の定期点検を心がけましょう。
補聴器による聞こえの改善

補聴器の使用を始めると、多くの方が生活の質の向上を実感されます。
その理由は、失われていた音の世界が徐々に戻ってくることにあります。家族との会話が自然に楽しめるようになり、外出時の不安も軽減されていきます。
ただし、補聴器に慣れるまでは周囲の音が気になりすぎたり、自分の声が違って聞こえたりすることもあります。これは、長い間聞こえていなかった音を脳が認識し直す過程であり、誰もが経験する自然な段階です。
そのため、補聴器に慣れることに焦らずじっくりと取り組むことで、より自然な聞こえを取り戻すことができます。
補聴器装用の効果
多くの方が実感している改善効果として、まず家族とのコミュニケーションの変化が挙げられます。食事中の会話が自然に楽しめるようになり、お孫さんの高い声も聞き取りやすくなることで、家族との時間がより豊かになります。
また、レストランでの友人との会話や講演会、映画鑑賞なども気軽に楽しめるようになり、社会活動の幅が広がります。
このように、補聴器の使用は単なる聞こえの改善だけでなく、生活全般の質の向上につながります。ご家族や周囲の方々とのコミュニケーションが円滑になることで、より積極的な生活を送れるようになります。
リハビリテーション
補聴器に慣れるまでには時間が必要です。専門家のサポートを受けながら、段階的に使用時間を延ばしていくことをおすすめします。最初は1日2時間程度から始め、徐々に装用時間を増やしていきましょう。
専門家によるサポート
補聴器は一度購入して終わりではなく、継続的な調整とケアが必要な医療機器です。
聴力は時間とともに少しずつ変化していくため、定期的な聴力測定と補聴器の微調整が欠かせません。また、生活環境や季節の変化によっても、最適な設定はそれぞれです。
例えば、仕事環境での聞こえの悩みや、趣味の時間をより楽しむための細かな調整など、一人ひとりの生活に合わせた的確なフォローを行います。
このような専門家による継続的なサポートを受けることで、補聴器の性能を最大限に引き出し、快適な聞こえの状態を長く維持することができるでしょう。
難聴と補聴器の基礎知識|まとめ
難聴は早期発見・早期対応が重要です。気になる症状がある場合は、まずは専門家に相談することをおすすめします。補聴器の選び方や使い方は人それぞれ異なりますが、専門スタッフのサポートを受けることで、最適な聞こえの環境を作ることができます。
愛知県補聴器センター・岐阜県補聴器センターでは、お一人おひとりの症状や生活環境に合わせたカウンセリングを行っています。
難聴でお悩みの方は、ぜひ一度ご相談ください。早期の対応が、より良い聞こえの回復につながります。