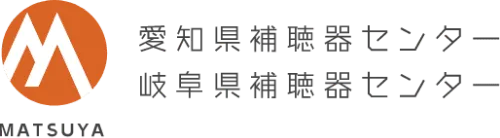公開日:
補聴器を検討する際、「ポケット型補聴器は価格が手頃で使いやすい」というイメージをお持ちの方も多いのではないでしょうか。
かつては主流だったポケット型(ボックスタイプ)の補聴器ですが、現在の補聴器市場では全体の約3%程度にまで減少しています。
その背景には、操作の簡便さという利点の一方で、いくつかのデメリットが存在するためです。
この記事では、ポケット型補聴器の特徴を詳しく解説し、より快適な聞こえを実現するための補聴器選びのポイントをご紹介します。
ポケット型補聴器の基本的な特徴

ポケット型補聴器は、その名の通り本体をポケットに入れて使用する補聴器です。
「ウォークマン」や「携帯ラジオ」のような箱型の本体に、イヤホンがコードで繋がっている形状をしており、「ボックスタイプ」と呼ばれることもあります。
ポケット型補聴器の最大の特徴は、本体が大きいため操作がしやすい点です。
音量調整のダイヤルやボタンが見やすく配置されており、細かい作業が苦手なご高齢者でも扱いやすくなっています。
また、大きな本体を採用していることで、単3電池や単4電池などの一般的な電池が使用でき、電池の持ちも比較的長いという利点があります。
さらに、マイク部分(音を拾う部分)と本体が離れているため、「ハウリング」と呼ばれる不快な音が起こりにくいという特徴もあります。
ポケット型補聴器のデメリット

ポケット型補聴器は操作性の良さがある一方で、現代の補聴器に求められる機能や性能面では多くの制約があります。
ここでは「聞こえの質」に関わるデメリットについて詳しく見ていきましょう。
聴力に合わせた細かな調整ができない
ポケット型補聴器の最大のデメリットは、個人の聴力特性に合わせた細かな調整が難しい点です。
現代の補聴器は、聴力検査の結果に基づいて周波数ごとに最適な増幅ができますが、ポケット型補聴器ではそのような調整が限定的です。
一部のトリマー式ポケット型補聴器では高音域と低音域の簡単な調整は可能ですが、現代のデジタル補聴器のような複雑な音響処理はできません。
そのため、必要な音が十分に聞こえず、逆に雑音だけが強調されるといった状況が生じやすくなります。
聴力低下のパターンは人それぞれ異なるため、こうした個別調整ができないことは、補聴器の効果を大きく制限してしまい、ご年配の方に多い感音性難聴では、単に音を大きくするだけでは難聴の改善に繋がらないケースが多いです。
難聴と補聴器の基礎知識についてはこちらの記事もチェックしてみてください。
雑音や環境音を拾いやすい
ポケット型補聴器は基本的に周囲の音をまるごと拾って増幅する仕組みになっているため、騒がしい環境では会話の声と周囲の雑音を区別せずに増幅してしまい、かえって聞き取りにくくなる事があります。
最新のデジタル補聴器には雑音抑制機能や指向性マイク機能が搭載されていますが、ポケット型補聴器では未搭載か、あっても性能が限定的です。
例えば、最新の補聴器では12チャンネルのデジタル処理により雑音と音声を分離し、雑音部分を抑えることができますが、ポケット型補聴器にはそのような高度な機能が備わっていません。
また、ポケットに入れて使用するため、衣服との摩擦音も拾いやすく、それが不快な雑音として聞こえてしまうこともあります。
これらの問題により、複数人での会話や騒がしい場所での使用に適していないという点が大きな制約です。
見た目やコードの煩わしさがある
ポケット型補聴器は、本体を胸ポケットに入れたりネックストラップで首から下げたりして使用するため、外見上も目立ちやすいという問題があります。
補聴器の使用を周囲に知られたくない方にとっては、この点が大きなデメリットです。
また、イヤホンとのコードが邪魔になることも多く、日常生活での動作の際に引っかかったり、前かがみになった時にコードが垂れて作業の邪魔になったりします。
さらに、スポーツをする機会が多い方や外出が多い方にとっては、このコードの存在が大きな不便を生じさせるため、ポケットのない服を着る場合には、補聴器の携帯方法にも工夫が必要です。
現在では販売モデルが限られている
ポケット型補聴器は、日本国内の補聴器市場において出荷台数の約2.8%程度と非常に少なくなっているため、製造メーカーや取り扱いモデルも限られており、選択肢が少ないという問題があります。
また、販売店によっては取り扱いがないケースも多く、購入後のサポートやメンテナンスの面でも不便を感じることがあります。
補聴器は長期間使用するものであり、アフターケアの充実度も重要な選択基準となりますが、ポケット型補聴器ではその点でも制約が大きいと感じるでしょう。
これらのデメリットを考慮すると、ポケット型補聴器は特定の条件下(家の中で比較的雑音が少ない環境で、使用者が頻繁に動き回らないような状況)でのみ有効に活用できる補聴器と言えます。
補聴器選びで後悔しないための補聴器の選び方
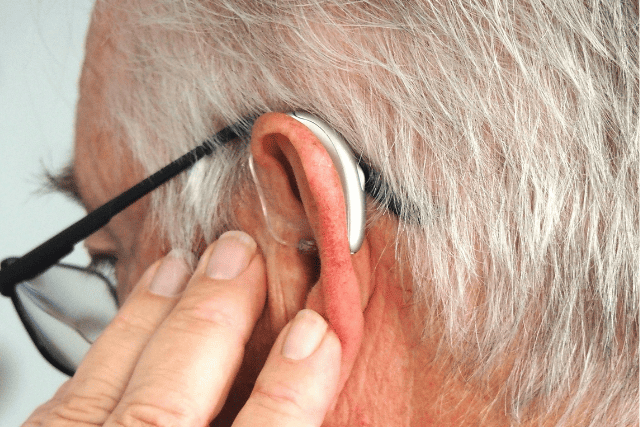
ポケット型補聴器のデメリットを理解した上で、より快適な聞こえを実現する為の補聴器選びについて考えてみましょう。
現在の補聴器市場では、耳かけタイプと耳あなタイプが主流となっており、それぞれに特徴があります。
耳かけタイプの補聴器は、取扱・操作がしやすく、着け心地が良いという特徴があり、本体が耳の後ろにかかり、透明なチューブで音を耳に届ける構造になっています。
閉塞感が少なく長時間装用しても疲れにくいため、初めて補聴器を使用する方にもおすすめです。
一方、耳あなタイプの補聴器は、耳の穴に収まるタイプで、外見上目立ちにくいという大きなメリットがあります。
また、耳の形に合わせてオーダーメイドで作られるため着けやすく、本来の耳の位置で音を聞くことができるため、自然な聞こえ方が期待できます。
最新の補聴器には、以下のような優れた機能が搭載されています。
- 聴力に応じた細やかなフィッティング機能
- 雑音抑制機能と会話強調機能
- Bluetooth接続によるスマートフォンとの連携
- 自動音量調整機能
最新のデジタル補聴器では、10~24チャンネルのデジタル処理により雑音と音声を分離し、騒がしい場所でも会話を聞き取りやすくする機能が搭載されています。
また、Bluetooth機能を搭載した補聴器では、スマートフォンからの通話や音楽を直接補聴器で聞くことも可能です。
自分に合った補聴器を選ぶためには、専門の補聴器販売店での聴力測定と試聴が重要です。実際に装着して音質や装用感を確認することで、長期間快適に使用できる補聴器を見つけることができます。
まとめ|ポケット型(ボックスタイプ)補聴器の特徴とは
ポケット型補聴器は、操作の簡便さや比較的安価な価格設定という利点がある一方で、聴力に合わせた細かな調整ができない、雑音処理が不十分、コードの煩わしさがあるなど、多くのデメリットを抱えています。
補聴器は単に音を大きくする装置ではなく、個人の聴力特性に合わせて最適な音を届けるための大切な機器です。
会話の聞き取りをより改善するためには、雑音抑制や指向性マイクなどの高度な機能が重要な役割を果たします。
現在主流となっている耳かけタイプや耳あなタイプの補聴器は、コンパクトで目立ちにくく、聴力に合わせた細やかな調整ができます。
また、Bluetooth接続などの便利な機能も搭載されているため、聞こえの改善だけでなくさまざまなサポートに対応しています。
補聴器は長期間使用するものですから、費用だけでなく、聞こえの質や着用感、店舗のアフターフォローの充実度なども含めて判断することが大切です。
まずは専門の補聴器販売店で無料相談や試聴などを行ってみて、ご自身に最適な補聴器を見つけることをおすすめします。
愛知県・岐阜県にお住まいの方で、補聴器の購入についてお悩みなら、愛知県補聴器センター・岐阜県補聴器センターにご相談ください。