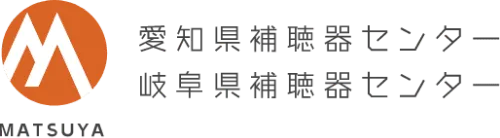公開日:
更新日:
年齢を重ねるにつれて「最近、聞き返すことが多くなった」「テレビの音量を上げがち」といった変化を感じていませんか?
一方で、同じ世代でも聞こえに問題がない方もいらっしゃいます。なぜこのような違いが生まれるのでしょうか。
この記事では、耳が遠くなる人とならない人の特徴と違い、聞こえを守るための具体的な対策について詳しく解説します。
将来の聞こえに不安を感じている方や、すでに変化を実感している方は、ぜひ参考にしてください。
目次
耳が遠くなる人の特徴とは?

耳が遠くなる人には、いくつかの共通した特徴があります。
これらの要因を理解することで、自分自身の聞こえのリスクを把握し、適切な対策を講じることができるでしょう。
ここでは、耳が遠くなる人の特徴についてご紹介します。
加齢による聴力低下(加齢性難聴)
加齢による聴力の低下は、40歳代から始まり、一般的に高音域から聞こえにくくなります。この現象は「加齢性難聴」と呼ばれ、内耳にある音を感知する有毛細胞が年齢とともに損傷・減少することが主な原因です。
加齢性難聴は一度進行すると根治が困難になるため、早期からの対策が不可欠です。
特に、高音域の聴力レベルは確実に下がってくるため、40歳代のうちはあまり自覚がなくても、将来を見据えた予防策を講じることが大切になります。
生活習慣が悪い
生活習慣の乱れは、聞こえの衰えを早める大きな要因のひとつです。
喫煙や飲酒、糖尿病・高血圧・高脂血症といった生活習慣病に加え、日常的に騒音の中で長時間過ごしてしまうことも、耳への負担を大きくします。
これらの影響により、耳への血流が妨げられたり、聴覚に関わる神経にダメージが加わったりする可能性があります。
特に、内耳への血液循環が悪くなったり、酸素が不足する状態が続くと、音を感じ取る「有毛細胞」が傷つきやすくなり、加齢にともなう聴力低下を早めてしまうおそれもあるのです。
耳掃除をしすぎ・耳垢の詰まりがある
過度な耳掃除や耳垢の詰まりも、聞こえに影響を与える要因ですが、一方で、耳掃除のしすぎも問題となります。
耳掃除は2週間から1ヶ月くらいの頻度で十分であり、外耳道の入り口から1cm以内の見える範囲の耳垢を綿棒でそっと拭き取る程度にとどめておきましょう。
耳が遠くならない・なりにくい人の共通点

耳が遠くなりにくい人には、いくつかの共通した特徴があります。
これらの習慣を身につけることで、聴力低下のリスクを大幅に軽減できるので耳が遠くなる人との違いを見ていきましょう。
生活習慣が整っている
耳が遠くなりにくい人は、規則正しい生活習慣を心がけていて、適度な有酸素運動を日常生活に取り入れることで血流を改善し、内耳の健康を保つことができます。
食生活では、塩分やコレステロールを控えた食事を心がけ、抗酸化作用のある食事やサプリメントの摂取も効果的です。
イヤホンや大音量を避ける習慣がある
大音量での音楽鑑賞やテレビ視聴を避ける習慣があります。
不必要な強大音でテレビやラジオを聞かないことが重要で、大きな音に聞き慣れてしまうと小さな音が耳に入りにくくなってしまいます。
イヤホンやヘッドホンで音楽を聞く際は、1時間連続使用後には10分の休憩を取るようにしましょう。
早期発見からの予防を行っている
耳が遠くなりにくい人は、定期的な聴力検査を受け、早期発見・早期対策を心がけていて、1年に1度は耳鼻咽喉科を受診することで、耳垢栓塞などの問題を早期に発見し、適切な処置を受けています。
定期的な検診により、聞こえの変化を客観的に把握し、必要に応じて適切な対策を講じることが可能になるのです。
耳が遠くなることを防ぐための予防法

聴力低下を防ぐためには、日常生活での具体的な予防策が重要です。
以下の方法を実践することで、聞こえを長期間維持することができるでしょう。
イヤホンよりヘッドホンを選ぶ
音楽を楽しむ際は、イヤホンよりもヘッドホンを選ぶことが推奨されます。イヤホンをつけ大きな音を流していると、音を聞き取る有毛細胞が徐々に壊れていきますが、ヘッドホンは鼓膜への音圧が分散されるため、聴力保護の観点から良い選択です。
ヘッドホンを使用する際も、音量は全体の60%以下に設定し、1時間おきに耳を休ませる時間を設けることが大切になります。
大音量でテレビや音楽を聞かない
日常生活で気をつけたいのは、テレビや音楽の音量設定です。
聞こえにくいからといって、不必要に音量を上げてしまうのは避けたほうがよいでしょう。
大きな音に慣れてしまうと、耳がその音量に順応してしまい、小さな音がさらに聞き取りにくくなることがあります。
結果として、ますます音を大きくしないと聞こえにくくなる、という悪循環に陥ってしまうのです。
また、大音量の環境に長くいると耳に負担がかかるため、その後は静かな場所でしっかり休ませることが大切です。
耳の健康を守るためにも、音の出る環境との付き合い方に気を配っていきましょう。
定期的に耳鼻科で検診を受ける
聴力の維持には、定期的な専門医による検診が不可欠です。1年に1度は耳鼻咽喉科を受診し、聴力検査を受けることで、聞こえの変化を早期に発見できます。
また、耳垢栓塞などの問題も専門医による適切な処置で解決できます。
基本的な生活習慣の見直し
聴力保護のためには、基本的な生活習慣の見直しが重要です。以下の点を心がけることで、聞こえを長期間維持できます。
- 禁煙
- 適度な運動
- バランスの良い食事
これらの生活習慣を身につけることにより、生活習慣病の予防にもつながり、結果として聴力低下のリスクを軽減できます。
耳が遠くなっていると感じたら?

すでに聞こえの変化を自覚しているにも関わらず、「まだ大丈夫」と先延ばしにしてしまう方が少なくありません。しかし、聞こえの問題を放置することで、日常生活に深刻な影響が生じる可能性があります。
ここでは、耳が遠くなる人が適切な対策を取らずに放置することで生じる様々なリスクと、聞こえの改善に向けた効果的な解決策について詳しく解説します。
放っておくと様々なリスクが生じる
聞こえの問題を放置すると、日常生活に深刻な影響を与えてしまいます。聞き返しが増えることで、家族や友人とのコミュニケーションが困難になり、社会的な孤立につながる可能性があります。
また、耳が遠くなる人にとって難聴は認知症の最大の危険因子の一つとされており、早期の対策が重要です。
早めの補聴器購入がおすすめ!
今までとの聞こえの違いを感じたら、早めの補聴器導入を検討することが重要で、補聴器の使用により、対面でのお話や離れたところでの呼びかけ、物音などが今までよりよくわかるようになります。
また、聞こえやすくなるという部分だけでなく、聞きにくいことで生じていた不安が減るという効果もあります。
補聴器購入をする時は専門相談員に相談しましょう
補聴器の購入を検討する際は、必ず専門の相談員に相談することが重要です。
補聴器に関する専門職の資格には、「認定補聴器技能者」と「言語聴覚士」の2種類があり、補聴器や聞こえに関する深い知識を持っているため、一人ひとりの聞こえに合わせた適切なサポートを提供できます。
愛知県補聴器センター・岐阜県補聴器センターでは、認定補聴器技能者が在籍している店舗がございます!
相談から購入、補聴器のケアまでサポートさせて頂きますので、是非一度ご相談ください。
まとめ | 耳が遠くなる人とならない人の違いとは?
耳が遠くなる人とならない人の違いは、日常の生活習慣と予防に対する意識の差にあります。加齢による聴力低下は避けられない部分もありますが、適切な予防策により、その進行を大幅に遅らせることが可能です。
生活習慣病の管理、大音量の回避、定期的な検診、適度な運動など、日頃からの心がけが聞こえの健康を左右します。
愛知県・岐阜県にお住まいの方で、すでに聞こえの変化を感じている方は、愛知県補聴器センター・岐阜県補聴器センターにご相談ください。
聞こえは生活の質に直結する重要な感覚です。今回ご紹介した予防法を実践し、必要に応じて専門家に相談することで、豊かな聞こえのある生活を長期間維持していきましょう。
\岐阜県・愛知県で補聴器の購入なら/